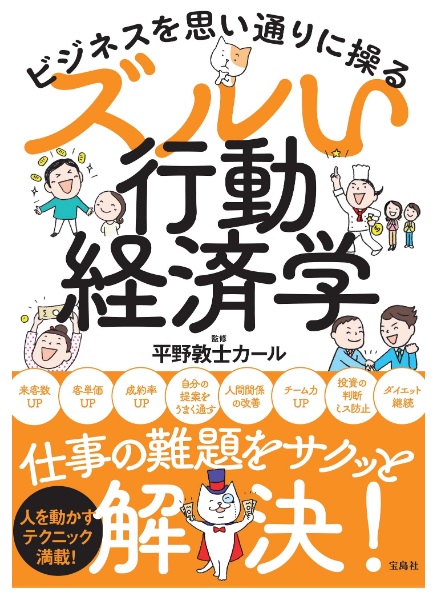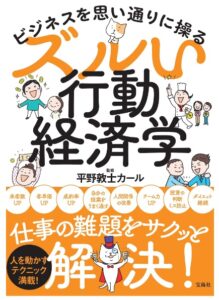
新動画講座
★カール経営塾動画★行動経済学基礎編 50分で行動経済学の基礎をマスター
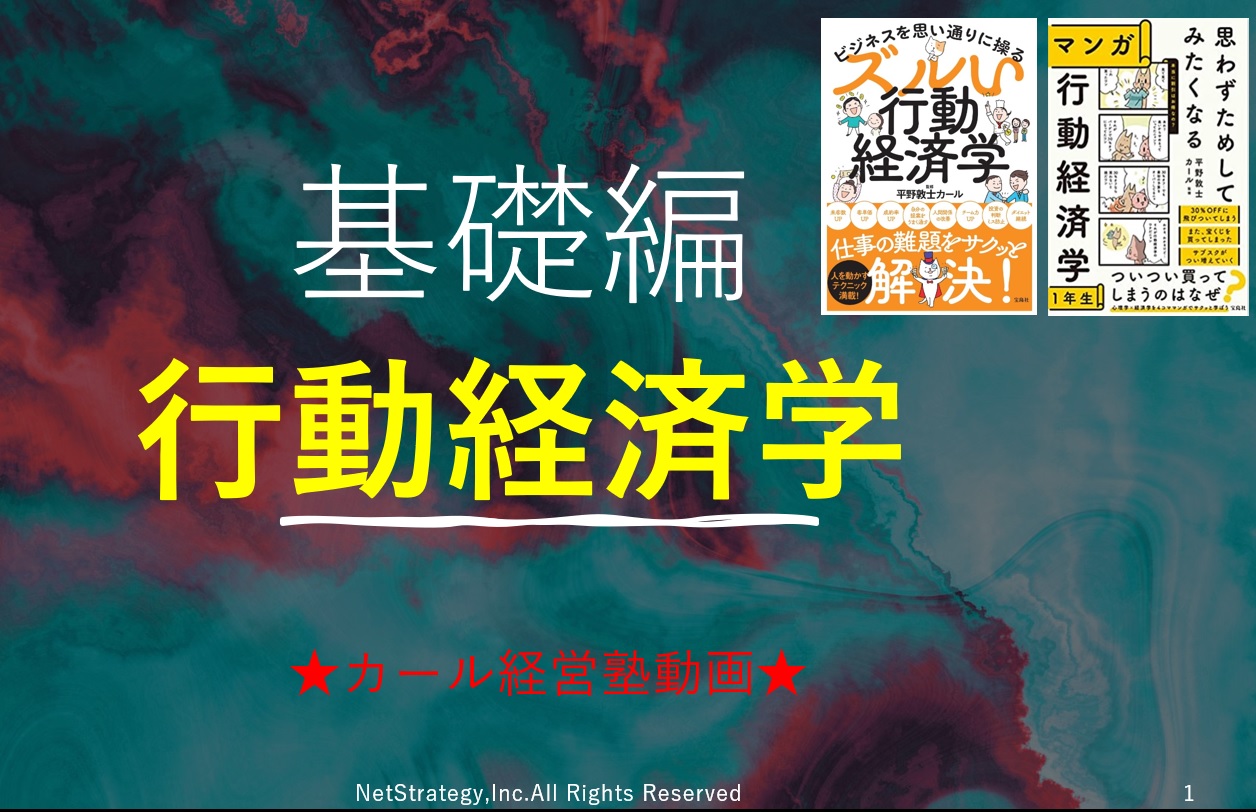
御礼!2冊連続10万部突破へ!PR
行動経済学とは何かを簡単に理解する方法としては、用語と具体的な例で覚えることです。私は東京大学経済学部出身ですが経済学というとマクロ経済やミクロ経済でした。
行動経済学は新しい学問ですがノーベル経済学の受賞者が2002年から立て続けに出たことから注目された学問です。実際私たちの日常生活でも取り入れられています
とくに面白いのは、ナッジというひじでヒトをつつくという意味の方法は人々を強制や罰則ではなく自然に行動を促す方法として活用されています。例えばレジの前に〇がいくつか書かれているとそこに列を並ぶ人が自然とソーシャルディスタンスを保つように並ぶ例やトイレにハエの絵を的として書いてあると的を狙って用を足す人が増えてトイレが綺麗に使われるようになっていたりと面白い例はたくさん身近な日常生活で活用されています。さらにマーケティングでも活用されていますのでぜひ基礎を理解してみてください
行動経済学についての 本もたくさん出ていますが、難しい専門書を読む前におすすめしたいのは小生の二冊の本です(笑)
おかげさまでBBMでご紹介いただき発売前にAmazon新着1位になりました
- ノーベル経済学賞で注目される行動経済学
- ナッジ理論
- 行動経済学とは
- 「ヒューリスティック」
- 「アノマリー」
- 「損失回避」「心理会計」
- 「初頭効果」
- 「初頭効果」「ピーク、エンドの法則」
- 「親近効果」 新しい情報が有効
- 「ハーディング現象」「バンドワゴン効果」
- 「バンドワゴン効果」
- 「群集心理」「サンクコスト」
- 「アンカーリング」
- 「コントロール欲求」
- 失敗は他人のせい、成功は自分の手柄 人は支配したがる生きもの
- 「比率バイアス」「確実性バイアス」
- 「決定の重みづけ」
- 「穴馬バイアス」
- 「プロスペクト理論」
- 「選択のパラドックス」
- 「因果関係の過大評価」
- 「双曲割引モデル」
- 「利用可能ヒューリスティック」
- 「単純接触効果」
- 「自由な選択」を導くナッジ理論 思考のくせを利用する
- 「内発的モチベーション」「外発的モチベーション」
- 損失回避性
- デフォルト「オプト・イン」「オプト・アウト」
- 休暇の取得率を3倍にしたナッジ
- 「カクテルパーティー効果」
- 「ハロー効果」
- 「現在バイアス」
- 「出費の痛み」
- 「時間選好」
- 現状維持バイアス
- 無料は最強
- 損しても売らない心の動き「保有効果」とは?
- 「損失回避性」参照点
- 「認知的不協和」
- サンクコスト(埋没費用)効果
- 「フレーミング効果」
- 極端の回避性
- 行動ファイナンス
- リスク回避
- 「おとり効果」
- 「参照点」
- 端数価格と威光価格・ウェブレン効果
- フレーミング効果
- プラシーボ効果 固着性ヒューリスティック
- イケア効果
- 現状維持バイアス
- 「返報性」「サンクコスト効果」「保有効果」サブスクの罠
- 「同調効果」 クラウドファンディング ライブ配信
- サンクコスト効果 分冊百科
- How Can We Help?
- 経営学用語
ノーベル経済学賞で注目される行動経済学
伝統的な経済学に心理学をプラスして生まれた行動経済学。現代では経済のベーシックな考え方とされていますが、いつ頃生まれたのでしょうか? 行動経済学の基礎となる理論を最初に唱えたのは、イスラエル出身のふたりの心理学者でした。
1979年、心理学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーは「プロスペクト理論・リスクがある環境下での意思決定の分析」という論文を発表しました。合理的に行動することができない人の心を、心理学を用いて分析したこの論文で、ダニエル・カーネマンは2002年にノーベル経済学賞を受賞しています(共同研究者のエイモス・トベルスキーは1996年死去のため受賞できまず)。リスクを過小評価し、低い確率の期待を過大評価してしまうことをプロスペクト理論で明らかにしました
世の中は常に不確実なもの。そのなかにおいて、人はこの先をどのように予測し、どのように行動するのかを論じたプロスペクト理論は、その後の行動経済学の発展に大きく寄与。伝統的な経済学ではアノマリー(例外)とされてきた事象についても、徐々に説明がなされるようになったのです。
ナッジ理論
プロスペクト理論を構築した心理学者のダニエル・カーネマンが2002年にノーベル経済学賞を受賞して以降、行動経済学を論じる学者たちが次々とノーベル経済学賞を受賞しました。
2013年に受賞したのは、アメリカの経済学者のロバート・シラーでした。株式を中心とした金融市場は、理論だけで未来を想定してもその通りにはならないことを解明したのです。
2017年には、アメリカの行動経済学者のリチャード・セイラーがノーベル経済学賞を受賞しています。セイラーは、ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーが唱えた「プロスペクト理論」に早くから注目し、伝統的な経済学ではアノマリーとされていたことの矛盾をつきました。そして、自らの理論である「ナッジ理論」を生み出し、ノーベル賞受賞となったのです。ナッジ理論は、今や行動経済学の中心的な考え方となり、世界中で注目されています。そして、セイラー自身も行動経済学の第一人者といわれているのです。
リチャード・セイラーが提唱した「ナッジ理論」
ナッジとは、隣の人を肘で小突いて気づかせるといった意味があります。要するに、ああしなさいこうしなさいと強制するのではなく、さりげなく意識させるように誘導し、いい方向へ行動を促すということです。
たとえば、子どもの頃に、親から「早く帰ってきなさい!」と強くいわれればいわれるほど帰りたくなくなるのに、「おいしい晩ごはん作って待ってるよ」といわれると早く帰りたくなった、という経験はありませんか? これが「ナッジ」です。
デパートなどのトイレの壁に「いつもきれいに使っていただき、ありがとうございます」という張り紙がしてあります。これは、「汚すな!」といった強制的な言葉を突き付けるより、きれいに使わなくてはいけないという気持ちを呼び起こす、ナッジ理論の活用といわれています。このように、ナッジ理論は、すでに私たちの日常生活に広く取り入れられているのです。
行動経済学とは
「ホモ・エコノミカス(合理的な経済人)」から豊かな感情を持つ人へ
では、なぜ伝統的な経済学から行動経済学が生まれたのか、ふたつの違いはどこにあるのでしょうか?
経済学では、お金を稼ぎ、お金を使い、経済を動かしていくのは人間そのものである、という考え方はほとんど無視されてきました。
伝統的な経済学において想定されてきた人物像は、常に自分の利益になることを考え、それをもとにムダなく行動し、他人のことなど考えずに自分中心に生きていくような、カチンコチンの堅物。迷ったり、悩んだり、喜んだり、アツくなったりといった豊かな感情を一切持たない、ロボットのような人間が経済を動かすと考えられてきたのです。
こうした人物像は、「ホモ・エコノミカス(合理的な経済人)」と呼ばれ、経済学の根幹となってきました。しかし、世の中に多様性が広がり、新しいビジネスが生まれるにしたがって、こうした人物像では理論が成り立たなくなってきたのです。
たとえば、おいしいラーメンを食べるために、行列に並んで何時間でも待つことができる人がいます。この時間を使って仕事をすれば収入がアップするかもしれないのに、それを捨ててでもラーメンを食べるために時間を費やすのです。
よく内容を知らないのに行列に並んでしまうのは、みんなで並ぶというハーティング現象と、おいしいという評判によるバンドワゴン効果のなせるわざ
伝統的な経済学では、こうした人間の欲求や、趣味、趣向は加味されませんでした。人間は、自分の利益のみ追求する「超合理的」な生き物と考えられたからです。
しかし、行列して何時間でも待つといった人間の欲求をも研究する必要が出てきたのです。
そこで誕生したのが、行動経済学でした。行列に並ぶ気持ち、何時間でも待てる気持ち、食べたあとの気持ちなどを分析し、それがラーメン店のビジネスにどう関わっているかを、理論づけることが可能になったのです。
このように、人の気持ちや行動を経済と重ね合わせるために用いられたのは、心理学でした。心理学では、利益がないのについやってしまう気持ちや、他人に左右されてしまう行動、喜びや悲しみ、悩みや迷いなどを理論的に検証します。そしてそれが、経済にどう影響しているかを考えるのが、行動経済学なのです。
時間がないのに行列店に並びたくなる、安売りも好きだけど高級なものも買いたくなる、貯金しなくてはいけないけど趣味にお金を使ってしまうなど、人の日常は心が揺れ動くことばかりです。そう、人は「非合理的」な生き物なのです。
「超合理的」な人物像をもとに組み立てられてきた伝統的な経済学は、時代の変化とともに世の中とのズレが生じてきました。難解すぎて、経済の主役である企業人や消費者には受け入れがたいものでもありました。その反省から生まれたのが、人間は非合理的であるという前提で構築された行動経済学です。伝統的な経済学の理論をもとに、より実社会にフィットした学問として広く認められているのです。
「ヒューリスティック」
確率を直感的に高く見積もる 緻密な分析よりざっくり把握
知識や情報をもとに時間と労力をかけて考えず、直感的にぱっと全体像を理解して行動する心理です。
「代表性ヒューリスティック」
事業の成功率を考えるとき、「失敗する人は少ないのだから自分もうまくいく」と思うことはありませんか? 代表性ヒューリスティックとは、このように緻密な分析で成功率を割り出すのではなく、見聞きした大まかな情報だけで全体像をつかもうとすることです。
経済学と心理学のコラボで実用的に革新
伝統的な経済学では、バブルは説明がつかないために起こりえないとされてきましたが、現実には起こってしまったのです。そこで活用されたのが行動経済学です。株価を左右する投資家の心理も研究対象となり、行動ファイナンスという理論も構築されました。
行動経済学は心の揺れ動きを分析
伝統的な経済学は、人間の気持ちの揺れ動きや、不安定な精神状態などは加味されずに理論が成り立っています。
これに対して行動経済学は、「人は、やってはいけないとわかっていることでもやってしまう」「やろうと決めたことでもモチベーションを上げるのに苦労する」「感情や考え方は一定ではなく、変化することだってある」といった、誰にでもある、ごく当たり前な心の動きを分析します。そして、それを実証して理論を構築し、社会において活用しようとする学問なのです。
「アノマリー」
伝統的な経済学は、「人間は常に合理的に、自分の利益に向かって行動するもの」といった考え方で構築されています。ムダな行いはせず、感情の揺れ動きもなく、迷いも悩みもないといったパーソナリティーを想定し、経済が語られてきたのです。
こうした人物像を経済学では「ホモ・エコノミカス(合理的な経済人)」と呼んでいます。
なぜそうした仮定を置いたのか?は、人間の心は不安定で、さまざまなタイプが存在し、考え方も千差万別だからという理由にほかなりません。人間の複雑な心をひとくくりにして論じることは不可能だったため、あえて“超合理的”な人間を想定する方法を選択したのです。
一方、新たな経済学として誕生した行動経済学では、「人間はブレやすく“非合理的”なもの」と考えます。ダイエット中なのにラーメンを食べてしまう、セール中の看板を見ると不要なものまで買ってしまう、会議中に寝てはいけないのについウトウト……など、プラスに働かない“非合理的”な行動は誰にでもあるもの。やらなくてはいけないとわかっているのにできない、逆に、やってはいけないのにやってしまうといったブレも、よくあることです。こうした人間の心の動きを経済学に反映させたものが行動経済学です。伝統的な経済学においては「アノマリー(例外)」として扱われてきたものが、近年になって見直されてきたのです。
行動経済学を知ることにより、今よりさらに暮らしやすくなるヒント、ビジネスがうまくいくコツなど、さまざまなメリットが得られるでしょう。
行動経済学を知り、よりよく生きる!
「損失回避」「心理会計」
行動経済学には「心理会計」という言葉があります。支払う金額は同じでも、そのときによって高いと思ったり、安くてよかったと思ったりする心の揺れ動きです。
ランチ代は500円までと決めていると仮定しましょう。忙しくてハンバーガーで済ませた日は「こんなに働いていてもハンバーガーか」と不満を抱き500円を高いと思うかもしれません。逆に、おかずたっぷりの定食を味わうことができた日は「いいランチだった!」と500円を安く感じて満足するでしょう。このように、同じ金額に対して、得か損かの感じ方が違うことを心理会計と呼ぶのです。得したときの満足度に対して、損したときの不満度は約2倍といわれます(価値関数)。人は、こうした損失感から逃れたいと思うもので、これを「損失回避」と呼びます。
「現状維持バイアス」
安心感を求めるから
たとえば、コンビニで飲み物を買おうとして迷ったとき、これにしようと決める理由は何でしょうか? CMを見たことがあるから、友だちがおいしいといっていたから、と答える人は多いはず。こうした行動を「利用可能性のヒューリスティック」と呼びます。ヒューリスティックとは、心理学用語で、必ずしも正しい答えではないが、経験や先入観によって直感的にある程度正解に近い答えを得る思考法で「経験則」です。その商品について詳しく知らなくても、記憶に残っているものや、身近な人がすすめるものを信用するという心の動きです。
また、もっとおいしいもの、価値の高いものがあることがわかっているのに、なぜか同じものばかり買ってしまうという人も多いでしょう。この心理を「現状維持バイアス」と呼びます。新しいものより、今までと同じもので安心感を得ようとする心の動きです。同じ店で同じメニューばかり食べる人も、しかりです。
「初頭効果」
はじめに見た目で印象づける初頭効果 見た目が9割、第一印象が9割
最初に相手をどう思ったかは、その後の判断にも大きく影響するといわれます。最初に会ったときにいい印象であれば、いい印象からスタートします。悪い印象の場合は、その悪い印象をもとにしての判断が基本になります。
初対面で、最初の判断基準になるのは見た目です。つまり、見た目は初対面の印象を左右し、初対面の印象は、その人の印象全体を左右するということです。これは初頭効果というヒューリスティックです。
印象に残したいことを先にいうのが良い 伝え方によって相手が受け取る印象が変わります。
「売り上げが上がりました。ただ、純利益は下方傾向です」と聞けば「売り上げが上がっているならよし。純利益も下げないように頑張れ」ということになりがちです。それを「純利益が下がっています。売り上げはキープしていますが」と伝えると「利益が下がっている」という情報が、より強くインインプットされがちです。
「初頭効果」「ピーク、エンドの法則」
つまり、プレゼンや営業トークであれば、最初に相手にとってのメリットを伝えることが有効です。相手が「話を聞きたい」という気持ちから入ってくるからです。
さらに、相手を説得したい場合は「伝えたい部分で話を盛り上げる(ピーク)」「最後(エンド)を印象的に締める」とこともポイントです。
人は、何かがはじまるときにもっとも注意を傾けます。相手の話が一定時間続く場合、同じ集中力で聞き続けることは難しいのです。そこで、とくに伝えたいことを話すときは、その部分を盛り上げることが大切です。そして、もうひとつ記憶に残りやすいのが最後の部分です。
最初につかみ、重要な部分で盛り上げて(ピーク)、その後一気に締める(エンド)。これがうまくいくと、いいたいことを印象的に伝え、さらに記憶に残すことができます。そして、「初頭効果」と「ピークエンドの法則」というヒューリスティックを活用するわけです。
「親近効果」 新しい情報が有効
最初の情報が印象を左右するという初頭効果に対して、最新の情報が意思決定に影響する事象を親近効果といいます。
ひとつの物事に対していくつかの情報を与えられたときに、最後に自分に届いた情報によって答えを決めがちというヒューリスティックです。親近効果は近しい間柄の場合、より効果を発揮するといわれます。
初頭効果が「三つ子の魂百までも」だとしたら、親近効果は「一夜漬け」。
「ハーディング現象」「バンドワゴン効果」
流行も群集心理から生まれる
「ハーディング現象」みんなといっしょが居心地いい
「赤信号、みんなで渡ればこわくない」。
「いけないことも、集団ならできてしまう」という人間の心理を突いたところに面白さがあったわけです。イジメ 仲間外れになりたくない
みんながやっているから自分もする。しても大丈夫という思考が行動に結びつくことを「ハーディング現象」といいます。
私たちには群れたがるという心理(群衆心理)があります。羊の群れが道の分かれ目にさしかかると、最初にどちらかを選んだ羊にみんなが従い同じ方向に進みます。群れたい、みんなといっしょにいたいという群集心理がそうさせるのです。
「バンドワゴン効果」
人気のものは、よりよく見えるバンドワゴン効果
ハーディング現象は、流行の大きな要因となります。あるものの人気が上昇して、それがブームといわれるまでになったとき。普段はそれを気にしない人々、自分ひとりならそれをしてみよう、それがほしいと思わない人々までが、したり買ったりするレベルになったということです。無意識であっても、みんながやってしているからする。みんなが持っているから買うという行動が流行をつくるということです。
さらに、みんなに人気のもの、大勢に支持指示されているものはいいものだと感じる「バンドワゴン効果」も流行に大きく関わります。同じマンガであっても「歴代ナンバー1の売り上げ」といわれると、よりおもしろく感じる。しかもいい点、おもしろい点を探そうとする。それがバンドワゴン効果です。
よく内容を知らないのに行列に並んでしまうのは、みんなで並ぶというハーティング現象と、おいしいという評判によるバンドワゴン効果のなせるわざです。
1973年のオイルショックでは、全国的にトイレットペーパーの争奪戦が巻き起こりました。騒動の一因は「インフォメーション・カスケード」だと考えられます。カスケードとは階段状の滝のことで、ある情報や行動により、群集心理が刺激されて大きな流れ(ブーム)となることです。
「不足気味だから買っておこうか」が「今のうちに買っておいたほうがいい」になり「今買わないと大変なことになる」ということになっていきます。情報のカスケードがハーディング現象を引き起こすのです。
あるものに対して、実際の価値よりも価値があるように感じさせる。または価値判断のあいまいなまま行動を起こさせるというハーディング現象やバンドワゴン効果は、マーケティングにも利用されます。お店の前にイスを並べて行列ができる店だと思わせたり、SNSやYou Tube上のインフルエンサー(人気者)に「これが好き」と発信してもらうことでブームを起こすことを狙ったりします。
「群集心理」「サンクコスト」
スマホゲームに課金してしまうワケ → 群集心理ではじめサンクコストで続行
スマホを通じて仲間といっしょにゲームを楽しめば、群集心理で課金してしまう。そうして、お金も時間も使ってしまった後では、さらに冷静な比較検討が難しくなります。
一因は「サンクコスト効果」によるもの。サンクは「沈んだ」の意味で、これまでにかけたコストを考え、やめることでそれがムダになってしまうと感じることです。
「アンカーリング」
「アンカーリング」はヒューリスティックの一種です。アンカーとは錨のことで、最初にイメージづけられた情報が、その後の情報の判断基準になることをいいます。
商品の値札に500円とだけ書かれているよりも、1000円を消して500円と書かれているほうが安く感じる。最初の1000円がアンカーとなって、500円という金額が、半額になったもののように感じてしまうのです。
「コントロール欲求」
失敗は他人のせい、成功は自分の手柄 人は支配したがる生きもの
私たちは本能的に、周囲の状況を支配したいという欲求(コントロール欲求)を持っています。特に自己愛の強い人が抱くことが多いと言われます。そのためなにかが成功すると、自分の支配が及んだという満足感を覚えます。逆に、失敗するとほかに失敗の原因を探そうとします。物事の原因を決めたがる気持ちを「帰属理論」といいますが、コントロール欲求があるために、失敗は他者に帰属すると考え、成功は自分に帰属すると考えたがるのです。
コントロール欲求は集中や落ち着きにも関わってきます。うるさい場所で2つのグループに作業をさせるという実験では「騒音をやめさせることができる」という権限を片方にグループに与えます。すると実際には騒音を止めなくても、もう一方のグループより作業に集中できたという結果があります。
「比率バイアス」「確実性バイアス」
宝くじ「買わなければ当たらない」も100%
誰かが7億円を当てる確率は100% 確実性バイアス
実際に1〜3等が当たる確率は、0.000225%。この数字を見てどう思いますか? 高額当選の数がいくら多くても、実際にどれだけ当たるかは確率を見なければ測れません。けれど、当選数の多さで自分も当たるかもと思ってしまう。これが「比率バイアス」です。
しかも誰かが7億円を当てる確率は100%。当選者が出るのは確実という「確実性バイアス」も、宝くじをより魅力的に感じさせます。
「決定の重みづけ」
低い可能性により期待する不思議
人は小さな確率を過大評価するという傾向があります。客観的な確率は数字に表れているのに、そこに主観的な評価を加えてしまうのです。これを「決定の重みづけ」といいます。
飛行機事故は自動車事故よりも格段に低い確率ですが、自動車より飛行機が怖いという人は多いでしょう。事実としての確率に対し、主観的な評価で修正された確率が決定の重みです。
決定の重みづけでは、利益を考える場合に低い確率への過大評価が大きくなることがわかっています。つまり、低い確率である宝くじの当選に対して、人は実際の確率よりも高く評価してしまうのです。同時に高い確率(宝くじが外れる)への過小評価が大きくなるため、外れる確率は低く感じます。
「穴馬バイアス」
競馬で大穴を狙うのも同じ心理の働きです。穴馬というのは勝つ確率の低い馬。それなのにあえてその馬に賭けようとするのは、確率が低いものに過度な期待する比率バイアスが「穴馬バイアス」となるからです。
本来、勝つ確率が一番大きな本命馬に対しては、実際に勝つ確率よりも人気が低くなる傾向があります。ここに決定の重みづけが働いているのです。
しかも競馬の場合、勝つ確率の低い馬ほど、勝ちを当てたときの見返りが大きいという仕組みです。この仕組みも手伝って、競馬で負けが続いた場合、穴馬に賭けたくなるという心理が働きます。
「プロスペクト理論」
客観的に見れば、勝つ確率の低い馬に賭けることはリスクであり、これ以上負けたくなければ、勝つ可能性の高い本命馬に賭けるべきです。それでも損失を取り返したいという気持ちが、リスクを過小評価し、低い確率の期待を過大評価してしまう。これが「プロスペクト理論」です。
「選択のパラドックス」
選択肢が多すぎると迷って決められない。これが「選択のパラドックス」です。しかも、選択肢が多いほど、決定に対する満足度も落ちることがわかっています。無意識のうちに「本当はほかのもののほうがよかったのでは」ないかと考えてしまうからです。
マクドナルドが行った、1000種類以上の組み合わせから選べるセットのキャンペーンが失敗したのは「選択のパラドックス」と、「決定麻痺」が原因だといわれます。人は選択に労力を使うため、選択肢や選択の機会が多いと疲れて決定麻痺を起こすのです。アップル社の創業者、故スティーブ・ジョブズ氏が常に同じ服装をしていたのも、日々、服装に対する選択をしなくて済ませるためでした。
選択肢も選択の機会もほどほどがいいのです
「因果関係の過大評価」
経験が合理的な判断のジャマをする 人は自分の経験を過大評価しがち
自分や近しい人が実際に経験したことは強くイメージに残ります。そうした経験をあてにしすぎてしまうことを「因果関係の過大評価」といいます。
もちろん、経験を判断材料のひとつにするのは必要なことです。手っ取り早く判断する方法のひとつです。どんな材料による判断も、未来を的確に評価することはできません。それを知ったうえで、経験だけに頼らず、自分の経験が客観的に見てどれほどの意味をもつのかを見極め、経験と情報をバランスよく取り入れ判断をくだしましょう。
「双曲割引モデル」
先の11万円より今の10万円
今10万円をもらうか、1か月後に11万円をもらうか選ぶとしたら、あなたはどうしますか? 多くの人が今、10万円をもらいたいでしょう。ところが、1年後に10万円もらうか、1年と1か月に11万円もらうか聞かれれば、1年と1か月後に11万円をもらうという人が増えます。
1か月待てば1万円増えるという事実は同じでも、今から1か月と、1年待ったあとの1か月は感じ方が変わります。この変化の度合いが「双曲割引モデル」です。どちらも1か月待って10万円多くもらうという人は「時間整合性」のある人です。
「利用可能ヒューリスティック」
コンビニ数を多く感じる理由 親しみのあるものの存在感は大きくなる
歯科医院と美容院、コンビニエンスストアでは、どれがいちばん件数が多いと思いますか?
多くの人はコンビニと答えるのではないでしょうか。外を歩いていればあちこちで見かけますし、毎日のように利用する人が少なくありません。しかし実際は、歯科医院は全国で約6万8000件。美容院の数は約25万1000件。コンビニは約5万6000件です。データを見ても信じられないような気持ちかもしれません。
これは「利用可能ヒューリスティック」による判断違い。「利用可能ヒューリスティック」では、親しみを感じているもの、思い出しやすいものが優先されます。歯科医や美容院よりコンビニのほうが身近で頻繁に行くなために、数が多いように感じるわけです。
日常で使えるマーケティング
行動経済学の核と言われるもいれるヒューリスティックは、あいまいさやザックリととらえることであり、人間らしさであるともいわれます。私たちは必ずしも合理的な判断や行動をするわけではなく、気分や心理学的な要素によって人間の言動は成り立っています。
マーケティングにも応用できます
「単純接触効果」
何度も見たもの、触れたものに対して親近感を抱く「単純接触効果」があります。
とくに用事がなくても、相手とあいさつをする。ちょっとした雑談をする。その機会を増やして「よく会うな」と意識させたらしめたものです。
会話をする機会があれば、最初に相手の興味をひきそうな話で「初頭効果」をねらいます。話は長引かせすぎず、盛り上げたらサッと切り上げる「ピークエンドの法則」を活用。「もっと話していたかった」と思わせたら成功です。「あの人も、この人も行ったんですって」と「ハーティング効果」で、人気スポットや話題のイベントに誘うのもいいでしょう。
行動経済学はマーケティングだといわれるように、営業やプレゼンテーションで使える知識の宝庫です。
「自由な選択」を導くナッジ理論 思考のくせを利用する
子どもの頃、そろそろ宿題をやろうかな、と思っていたときに「宿題しなさい!」と言われてやる気がなくなってしまったことはありませんか?
人は、規則や命令で縛られると反発してしまいがちですがこうした人間の思考のくせをうまく利用して気分よく行動できる方法がナッジ理論です。
ナッジとは、英語で「ひじで軽くつつく」という意味です。隣の人の注意をうながすためにちょっと小突くイメージです。ナッジ理論は、ひじでつんつんとつつくように、行動変容をうながすことを指します。あくまでも他の選択肢を残した状態で、強制しないことがポイント。ノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー氏らによって唱えられました。
ナッジ理論の誘導は、「自分で選んだ」という満足感をもたらすため、気分よく行動できるのです。
トイレの的
空港など多くの人が利用する場所では、掃除は重労働。オランダにあるスキポール空港では、トイレ掃除の手間と費用を減らすため、男子トイレの小便器の内側に小さなハエの絵を描きました。一見、掃除とは関係ないように思えますが、なんとこのハエのおかげで、トイレの汚れが大幅に減少したのです。なぜでしょう?
それは、「的があると狙いたくなる」という人間のくせを上手に利用したから。便器に描かれたハエを見た多くの利用者が、ハエめがけて少し慎重に用を足しました。結果として、飛び散りが少なくなり、清掃の手間もコストも減ったというわけです。
このとき、誰も利用者に強制したり、ご褒美を出したりはしていません。多くの人の行動を自然に変えた、ナッジのお手本のような例ですね。
ナッジは、環境問題への取り組み SDG’sにも
先がけとなったのは、アメリカで行われた実験。各家庭に、その家と、よく似た家庭それぞれの電力消費量、そして節電のアドバイスを記載した「ホームエナジーレポート」を定期的に送りました。すると、約1.4~3.3%の節電に成功したのです。
エコ政策の実験は日本でも。ホームエナジーレポートのように、よく似た家庭、そして節電上手な家庭と比べたエネルギー消費量を通知する実験では、電気やガスの使用量が毎月約2%減少。また、車の走行状況をアプリで測り、エコドライブスコアのランキングや節約できたガソリン代などを知らせる実験では、燃費が最大14.5%改善されました。
ダイエットにもナッジ 音の鳴る階段で自然と健康な体に
食事制限や運動といった健康習慣の継続にも、ナッジ理論は力を貸してくれます。
富山県のコミュニティホールには、ピアノの鍵盤に見立てたデザインの階段があります。ポイントは、歩くとピアノの音が鳴る仕掛けになっていることです。横にはエスカレーターもあるのですが、ピアノ階段は楽しくて、「運動のため」と思わなくてもつい歩きたくなりますよね。楽しいことに惹かれる人間の性質をうまく使って、運動をうながす作戦です。
食事選択も、無意識のくせを利用してコントロールできます。バイキング形式の食事なら、席に近く取りやすい場所に野菜を、遠く取りにくい場所に肉料理や油ものを配置すると、利用者は自然と野菜多めでヘルシーな選択がしやすくなるのです。
イギリスでは、このくせに訴えかけるナッジで、納税率が劇的にアップしました。期限までに税金を払わなかった人に対して送る督促状に「イギリス国民のほとんどが期限内に税金を納めています。まだ納税していないあなたは少数派です」というメッセージを載せたのです。結果、罰則などを設けることなく、納付する人の割合を大きく上げることができました。 自分ひとりでは気が進まなくても、みんなが払っていると聞くと「同じようにしなければ!」と感じてしまうのです。
「内発的モチベーション」「外発的モチベーション」
罰金がモラルを邪魔してしまう?罰金16万円でも減らないポイ捨て
人が行動する動機は、大きく分けてふたつ。達成感やモラルなど自分の中にある「内発的モチベーション」と、報酬や称賛など外から与えられる「外発的モチベーション」です。お金を失う罰金も、外発的モチベーションのひとつといえます。
シンガポールでは、ポイ捨てに最高16万円相当の罰金が課せられます。高い罰金でポイ捨てはゼロ! かと思いきや、意外にも摘発者の減少は頭打ちでした。
これは、罰金という外発的モチベーションが、「街をきれいに保ちたい気持ち」という内発的モチベーションを打ち消したため。「お金を払えばポイ捨てをしてもよい」という意識が生まれてしまったのです。罰金は明快なモチベーションですが、それだけで行動を制御するのは、なかなか難しいようです。
損失回避性
人間には「新しいものを得られない」ことよりも、「今持っているものを失う」ことを避けたがるくせ、「損失回避性」があります。
立川市では毎年、大腸がん検診の未受診者へのメッセージを「今年この検診を受ければ、来年も無料でキットをお送りします」から、「今年この検診を受けないと、来年からキットをお送りできません」へと変更。すると、受診率が22.7%から29.9%にアップしました。
内容そのものは変わりませんが、「キットをもらう権利」に焦点を当て、それを失う可能性を強調することで受診をうながしたナッジの例です。
デフォルト「オプト・イン」「オプト・アウト」
いくつかの選択肢からひとつの行動を選ぶとき、その選択は初期設定に大きく左右されています。初期設定に、選んでもらいたい選択肢をもってくることを「デフォルト」といいます。
たとえば、ある選択肢に関して「同意」という行動をしてほしいときには、「同意」をデフォルトにしたほうがその選択率が上がります。「同意する場合はサインを」ではなく、「同意しない場合はサインを」とお願いし、なにも行動しなければ同意したことになる設定です。通販サイトに会員登録をするとき、初期設定の段階で「メールマガジンを受け取る」の項目にチェックが入っているのをよく見かけますよね。これはまさに、デフォルトを利用してメールマガジンの読者を増やすためのナッジです。
同意しないことが初期設定となっているものを「オプト・イン」、同意することが
初期設定となっているものを「オプト・アウト」といいます。
臓器提供に同意する人の割合は、国によって異なります。フランス、オーストリアなど、オプト・アウト形式で意思表示をする国の同意率は100%近く。一方オプト・イン形式の国では、日本が13%弱、デンマークが4%強など低い水準です。
オプト・アウト形式のほうが同意率が高くなるのは、「臓器提供に同意しません」という表明が大変だからです。何もしないという一番ラクな選択をすると、同意の意思表示になるというわけ。さらに、たとえば「同意しない場合は、提供したくない臓器を選んでください」という設定を追加すると、情報量が増えて思考の負担が大きくなり、より「同意しない」を選びにくくなります。
休暇の取得率を3倍にしたナッジ
中部管区警察局では、睡眠不足になる夜勤明けに、休暇取得をデフォルトとする仕組みを導入しました。休まない場合に申請を行うオプト・アウト方式です。「言いにくい、申請が面倒」という課題が解決され、休暇取得者は約3倍に増えました。
「カクテルパーティー効果」
パーティー会場などの人混みでも、会話をしていると、相手の声だけがよく聞こえますよね。逆に、周りの声が気になって目の前の人の話が耳に入らないこともあります。人は、聞くべきこと、興味のあることが頭に入ってくるように、意識を向ける情報を選んでいるのです。これをカクテルパーティー効果といいます。
ダイレクトメールに「〇〇区に住んでいる方限定のお得な情報」など、配布地域の名前を入れるのもカクテルパーティー効果を利用した例。自分の住んでいる場所のことが書いてあると、つい気になって見てしまう、開けてしまうのです。
「ハロー効果」
「ハロー」は、聖人の像などから差す後光を意味する単語。ハロー効果は、美しい外見や高い評判、権威ある肩書きなどがまるで後光のようにまぶしく光り、そのもの全体がすばらしいかのような印象を与えて起こります。
同じ健康についての情報でも、町のちいさなクリニックの医師が言うのと、有名な大学病院の教授が言うのでは、後者のほうが信頼できるような気がしませんか? 情報の本質を考える前に、私たちはなんとなく評価を決めてしまっているのです。
「現在バイアス」
時間の区切りを見直すのも効果的です。たとえば2か月後に終えたい仕事があるとします。ゴールが遠い業務は、つい着手が遅くなりがちですよね。結局、締め切り直前に作業がたまり、効率ダウンに。しかし、1週間ごとに進捗報告をすると決めると、すぐはじめたくなりませんか? 将来よりも目の前にあることを大きく評価する「現在バイアス」が働くので、目先に目標があると取り組みやすいのです。
「出費の痛み」
行動経済学者のダン・アリエリーは、人は、代金を支払うときには精神的苦痛を感じると説き、これを「出費の痛み」と名づけました。
痛みが最大になるのは、現金で支払うときです。しかし、電子マネーやクレジットカードを使った場合、引き落としはずっと後のことなので、「出費の痛み」は感じません。実際にはお金を使っているのに、その瞬間には苦痛を感じないため、買い物を心底楽しむことができ、ついつい財布の紐がゆるんでしまうのです。
「時間選好」
不動産屋さんの「月々の支払は家賃より安い6万円!」といったチラシに誘惑されて、家を買おうと思っていませんか? こうした住宅ローンは元本返済だけだと数年後に返済額が上がる可能性もあるので要注意です。なぜ、こうした広告に心が揺れ動くのでしょうか。そこには「時間選好」という心理が働いています。人は、目の前のメリットにもっとも価値を感じ、将来に得られるであろうメリットには価値を感じにくいという傾向があるのです。住宅ローンは月々の返済額が家賃より安いことに気をとられ、先々のメリット・デメリットまで考えられなくなるという心理を逆手にとった金融商品。冷静な判断を忘れずに。
現状維持バイアス
「いつでも半額!」の貼り紙を見てつい買ってしまうことがありますね!このとき、客側の心には「現状維持バイアス」が生まれています。今の状況を変えたくない、現状を維持したいと思う損失回避の心理です。このケースでいえば「半額のあの商品は使いやすい。売り切れると困るから、またあの店で買っておこう」という気持ちです。売り切れてもほかの店で買えばいいのですが、半額で買えないことに損失を感じ、現状を維持したいがために、また同じ店で買い物をするのです。
無料は最強
グーグル、ヤフー、フェイスブック、ツイッター、ラインなど、多くのインターネットサービスが無料で利用できますが、各企業はどのように利益を生んでいるのでしょうか? 実は、こうした企業は無料であることを大々的に掲げてユーザーを増やし、その一部を有料ユーザーとして獲得して利益を得ています。
人は無料のものに魅力を感じ、ほかに価値あるものがあったとしても無料のものを選択します。たとえば、1000円の高級菓子が300円に値引きされているのと、100円の駄菓子が無料で配られているのを比較すると、高級菓子のほうが価値があるのは明らかでも、多くの人が無料の駄菓子を選びます。インターネットサービス企業は、この心理を利用して世界規模でユーザーを獲得しているのです。
損しても売らない心の動き「保有効果」とは?
行動経済学の根幹となっている「プロスペクト理論」は、投資家の心理も読み解きました。投資家には、値上がりして利益が出た株は早く売りたいけれど、値下がりして損失が出ている株はすぐには売らず値上がりを待つ、といった傾向があります。
プロスペクト理論では、こうした投資家には「利益は早く自分のものにしたい。損失はできるだけ先送りしたい」という人の心理がそのまま当てはまると考えます。なぜ、損している株を持ち続けるのでしょうか。そこには「この株は上がると信じて買ったのだから、いつかきっと上がる」という思いがあるから。また、自分が大切にしているものの価値を高く見積もる「保有効果」も影響すると考えられます。
「損失回避性」参照点
プロスペクト理論では、利益を得たときの喜びと、損したときの悲しさを「価値関数」というグラフで表します。このグラフでは、縦軸で感情を、横軸で利得と損失をそれぞれ数値化しています。
価値関数では、同じ金額で得したときと損したときの感情を比較すると、損のほうが2〜3倍も重く感じることを表しています。人の心は弱いもので、ずっしりと重く感じる損からは逃れようとします。これを「損失回避性」といいます。価値関数では、参照点から離れるほどに感じ方が弱くなります。参照点とは利得と損失の判断を分ける基準のことでたとえば株式投資では購入時点の株価などが相当します。
「認知的不協和」
自信をもって取り組んだことが失敗すると、「うまくいくはずだったのに」という気持ちと失敗した現実が対立して、心のなかに「認知的不協和」が生じます。失敗したときの辛さは、成功した喜びより心に重くのしかかるため、人はそのストレスから逃れようとする傾向があります。そして、失敗の事実を見つめることを避け、「客の判断がまちがっている」「だれかが営業妨害したんだ」などと、自分に都合のいい言い訳を考えてしまうのです。
あれこれ言い訳を考えるより、失敗を認めて1歩前にを踏み出すほうが得策です。
サンクコスト(埋没費用)効果
「この事業には莫大な費用をかけてきたのだから、ちょっと業績が落ちたくらいでやめるわけにはいかない」と、無理して続けている案件はないでしょうか? 行動経済学では、すでに支払っていて回収できない費用を「サンクコスト(埋没費用)」と呼びます。投じた費用を諦めきれずに撤退できない、いずれ利益が出ると夢を見てやめるタイミングを逃しているといったケースを見かけますが、得策とはいえません。
ギャンプルもまたしかり。元手となったお金を取り戻そうとして賭け続け、やめられなくなってしまうのです。こうした心の動きを「サンクコスト効果」といいます。
サンクコストはきれいさっぱり忘れましょう
「フレーミング効果」
「タウリン1000mg」と「タウリン1g」の栄養ドリンクではどちらが効きそうでしょうか? 1000mgのほうがたっぷり入っている印象ですが、含有量はまったく同じです。このように、表現方法の違いによって印象が大きく変わることを「フレーミング効果」といいます。
極端の回避性
1000円と2000円の2種類と、1000円、2000円、3000円の3種類を用意した場合、どちらが儲かると思いますか? 正解は、3種類のメニューです。
人は、2択では価格の安いほうを選びがちで、3択では、7割以上が真ん中の価格を選ぶといわれます。2種類では1000円ばかりが売れ、3種類では真ん中の2000円が圧倒的に多く売れ、利益が増えるのです。その理由は「極端の回避性」にあります。人には、極端に安いもの、高いものを避け、中間を選択する傾向があると、行動経済学では分析しているのです。売りたい商品と一緒に安いものと高いものを並べて3択にすれば、ねらい通りの売上が期待できるというわけです。
行動ファイナンス
行動経済学を株式や金融に応用したものを「行動ファイナンス」といいます。
行動ファイナンスでは、株価は人の思惑によって変動すると考えます。ある企業の株価を見て、高いと思うか安いと思うか、買い時と思うか売り時と思うかは、投資家それぞれの判断です。過去に経験した高値・安値にとらわれる心の動きも反映します(アンカリング効果)。さらに、周囲の動向に流される群衆心理や、大きな災害や事件の発生が影響することも。キリのいい数字で売買が活発になることもあり、人の心理と株価は、常に密接な関係であることがわかります。
リスク回避
海外通貨を売買して利益を得るFX(外国為替証拠取引)。取り組みやすい仕組みも作られ、人気となっています。しかし、利益が出ないと悩む人が多いのも現実。プロスペクト理論では、その原因が明らかになっています。人は、利益が出ているときと損しているときでは、リスクに対する気持ちが変わります。利益が出ているときには、それを確実に手にしようと、さらなるリスクを避けようとします。
一方、損しているときにはいつか利益が出るだろうと期待し、リスクを持ち続けます。この心の動きを「リスク回避」と呼びます。FXは、株式に比べるとハイリスクな取引です。そのため、価格が少しでも上がるとその利益を確実に手にしようとする反面、価格が下がったときにはリスクをさらに持ち続けようとします。
「おとり効果」
「最新モデルより安いのはこちらです。でも、機能は少ないし、料理のできばえも劣ります」と伝えると、客はすんなりと最新モデル購入を決めるでしょう。
これは、行動経済学者のダン・アリエリーが実証した「おとり効果」です。引き立て役と比較することで、商品をより魅力的に見せるのです。これとは反対に、売りたい商品より高価な商品を提示する方法もあります。1パック500円のイチゴを売りたいなら、1000円のイチゴと一緒に並べるのです。500円のお得感が強調され、客が手に取りやすくなります。
「参照点」
行動経済学は、消費者の動きのヒントになるため、販売などの分野にしばしば活かされます。その代表的な例がテレビショッピング。テレビショッピングで扱う商品は、食品から家電までさまざまですが、売り方はどれもよく似ています。
よくあるのが、はじめに〇〇円という値段を出し、「これが特別割引で××円に!」とアピールすることです。最初から実際の値段だけを伝えればいい気がしますが、もとの値段も出すのは「参照点」を示す意味があります。というのも、人間の感じる価値の基準は状況に応じて変わるから。もとの値段を見せると、基準となる参照点が「買わないこと(=0円)」ではなく「もとの値段(〇〇円)」に変わるため、買い物をしてお金を払うにもかかわらず得をしたように感じるのです。
端数価格と威光価格・ウェブレン効果
1980円や298円などのキリの悪い値段設定は「端数価格」と呼ばれ、「安い」と感じさせる行動経済学のテクニックです。人が値段を見るとき、強い印象を与えるのは一番大きな桁の数字です。1980円なら、一番大きいのは1になります。よく考えると、1980円は、20円安いだけでほぼ2000円。しかし一番目につくのは1なので、1000円台というイメージが強まり、実際よりかなり安く感じるのです。
逆に、100万円などのキリのいい価格設定は「威光価格」といい、「高い」という印象を与えます。ブランド品や、高級外車など、「こんなに高額なのだからいいものだ!」と感じさせたい品物に効果的です。これを「ウェブレン効果」といいます。高いお金を払うほど、この作用は強まります。
フレーミング効果
おにぎり全品20%引きのセールをやっていたとします。あなたが買おうとしたおにぎりの元値は125円でした。一方コンビニに行くと、おにぎり全品100円というセールやっていました。なんとなく、コンビニで買ったほうが安いように感じませんか?
実際は、ふたつの店のおにぎりの値段は同じ。しかし、「125円の20%引き」といわれても値段がすぐにわからないため、安いことがピンとこないのです。逆に、「全品100円」という価格での表示はわかりやすく、安さをすぐにイメージできます。同じことでも表現のしかたで印象が変わる「フレーミング効果」をうまく使って、お得感を高めているのです。
プラシーボ効果 固着性ヒューリスティック
新薬開発の際、効き目を検証する過程で、新薬を投与する群と、効果のない偽薬(プラシーボ)を投与する群を比較して研究を行います。このとき、なんと偽薬でも症状が改善することが。「薬を飲んだから治る」という認識だけで、効果が出てしまうのです。これを「プラシーボ効果」といいます。
同じワインに、片や1000円、片や1万円の値段をつけてお店に出すと、飲んだ人は1万円のワインをおいしく感じることがあります。これもプラシーボ効果。お客さんは嘘をつくわけではなく、「ワインは高級なほどおいしい」という経験や知識から、1万円のワインを本当においしいと認識するのです。自分の知っていることや考えていることに影響される、「固着性ヒューリスティック」の一例といえます。
イケア効果
自分で手間ひまかけてつくり上げた成果を高く評価する傾向がありこれを「イケア効果」といいます。自分で組み立てた家具や、ひと手間かけたホットケーキには、値段以上の高い価値を感じるのです。
現状維持バイアス
サブスクを一旦はじめると、サービスを利用している状態が日常となります。すると、解約したら今まで持っていたものを失ってしまう気がして、抵抗を感じるのです。これは、「現状維持バイアス」のしわざです。また多くのサブスクでは、初回支払い時にカードなどの情報を入力したら、その後は自動で料金が引き落とされるシステムになっています。そのため、支払いの実感が薄く、出費の痛みを感じにくくなって、お金を払い続けてしまうのです。
「返報性」「サンクコスト効果」「保有効果」サブスクの罠
「成果が出なければ全額返金」「気に入らなければ返品無料」という文句を、英会話教室や通販サイトで見かけます。教室で講師が熱心に指導してくれたり、通販サイトから注文した服を配送してくれたりすると、「された親切に報いないと」という「返報性」の考えが生じます。また、解約でお金は戻っても、勉強の労力や服を選んだ時間は返ってきません。そのため、かけたコストを回収したいと思う「サンクコスト効果」も働きます。
さらに、自分が所有しているものの価値を高く感じる「保有効果」により、返品できるとしても、一度手元に置くと手放したくなくなります。これらの合わせワザで、実際に解約・返品するのは難しく感じるというわけです。
「同調効果」 クラウドファンディング ライブ配信
クラウドファンディングを行うサイトのほとんどが、支援者の出資額やコメントなどが誰でも見られる仕組みになっています。すると、周囲と同じ行動をしておきたい「同調効果」によって、「みんながこんなに出資しているなら自分もするべきだ」という気持ちになり、お金を払いたくなるのです。応援経済の名の通り「目標を持った人を応援する」というクラウドファンディングの性質には人助け的な感覚があって、利他性をかきたてます。一方で、出資者には基本的にリターンがあります。お礼の手紙、完成した製品、飲食サービスなど内容はさまざまですが、このリターンの約束によって互恵的な関係が生まれ、ただの寄付に消極的な人も気分よく出資を行えるのです。
ライブ配信者の発信も、視聴者の出資もリアルタイムでお互いに見えているという特徴があります。他の支援者がいつ、いくらのお金を出したのかがわかる仕組みはクラウドファンディングと同じです。「同調効果」が生じ、お金を払いやすい心理になります。
また、サイトによっては事前購入のアイテムなどのかたちで投げ銭を行う場合もあります。こうすると、投げ銭のタイミングと支払いのタイミングが変わるため、出費の自覚が薄くなり、つい多額の投げ銭をしてしまいやすくなるのです。
そして投げ銭でお金が集まるカギといえるのが、路上ライブのような双方向性の高さ。配信者が、投げ銭をした視聴者に対してライブ配信中に「○○さんありがとう!」などと名前を呼んで発言することもあります。まさにライブ配信の双方向性を活かしていますね。出資者は「応援が届いているんだ」という満足感を得られ、出資にも熱が入るというわけです。
サンクコスト効果 分冊百科
商品を売る企業が一番うれしいのは、お客さんが商品を買い、できれば買い続けてくれること。消費者の心理をうまく使ってそれを叶えているのが、ディアゴスティーニのような分冊百科です。創刊号が安めの価格になっており、買い始めやすいこと。2号以降は値段が上がりますが、創刊号を買ったため「サンクコスト効果」が働き、「買わないと、これまでのお金や組み立てた苦労が水の泡だ」と感じます。一度買ったら全部買わないと損した気がするビジネスモデルです。
更に詳しくは
★カール経営塾動画★行動経済学基礎編 50分で行動経済学の基礎をマスター
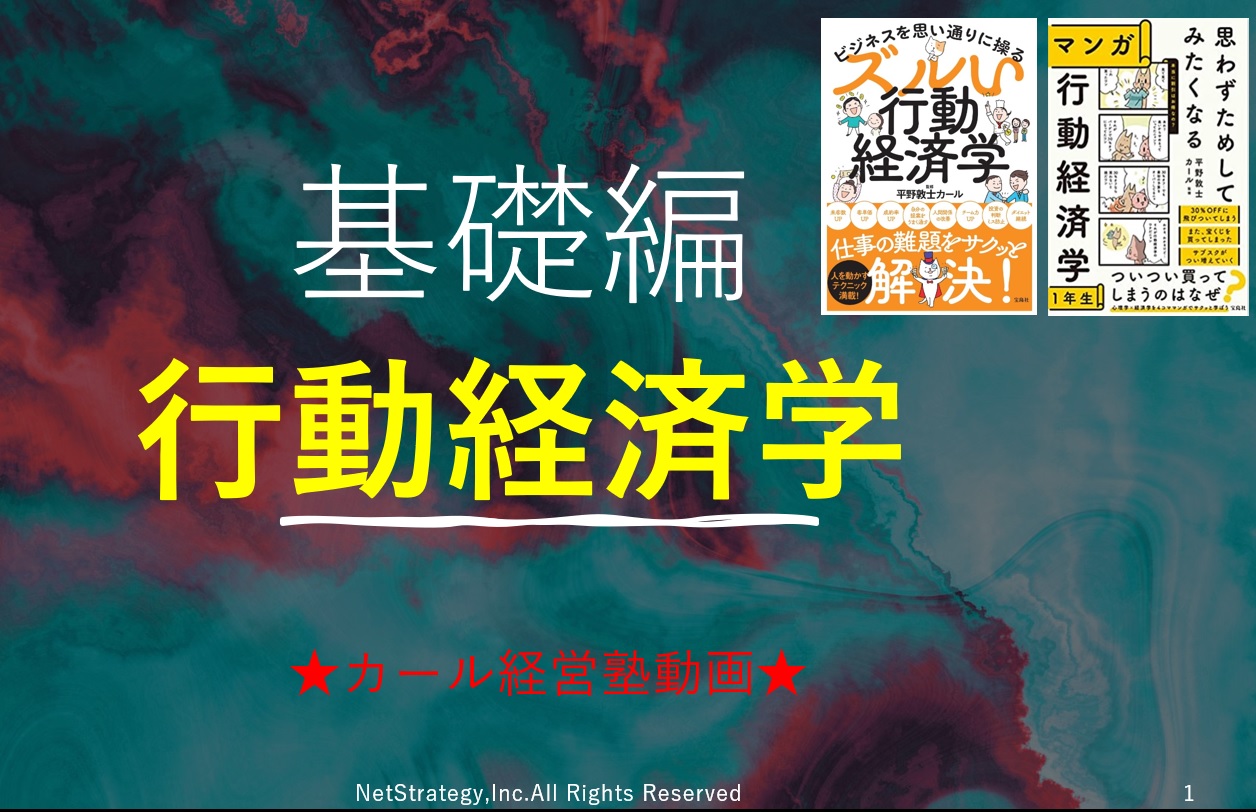
御礼!2冊連続10万部突破へ!PR
How Can We Help?
-
経営学用語
- AIサーバー GPUサーバー
- AI半導体AIアクセラレーター、ファウンドリー
- AI開発プラットフォーム
- GPU(画像処理半導体 Graphics processing unit)
- RAG (Retrieval Augmented Generation、検索拡張生成)
- インスタンス
- クラウドコンピューティング
- システムインテグレーター (Sler)
- シンギュラリティ (singularity)
- スケーリング則(Scaling Laws for Neural Language Models)
- ディープフェイク Deep Fake
- トランスフォーマー
- ファインチューニング
- マネージドサービス
- マルチモーダル
- 動画生成AI「Dream Machine」
- 大規模言語モデル (LLM) パラメーター数
- 生成AI
- EBITとEBITDAの違い
- NFT(Non-Fungible Token 非代替性トークン)
- SPAC スパック Special Purpose Acquisition Company 特別買収目的会社
- 「銀行業高度化等会社」とは
- 【決定版】企業価値算定DCF法CAPM ベータ値WACCとは
- オプション取引 コールオプション&プットオプション Option
- オープンAPI Open API
- キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)とは
- スワップ取引とは SwapTransaction
- テーパリング Tapering
- デリバティブとは derivative
- ハードフォークとソフトフォーク(暗号資産 仮想通貨)
- バリュー・アット・リスク Value at Risk(VaR)
- ビットコインとブロックチェーン Bitcoin&Block chain
- フィンテックベンチャー
- ブラック・ショールズ・モデル B&S Model
- リアル・オプション real option
- 一株当たり純資産とは Book-value Per Share(BPS)
- 会社のねだんの決め方~企業価値算定3つの方法 Valuation
- 会計とファイナンスの違い Accounting&Finance
- 債券とは 格付けとは
- 先渡取引とは Forward transactions
- 固定比率とは Fixed ratio
- 固定長期適合率とは fixed long term conformity rate
- 売上高営業利益率とは Operating Profit Ratio
- 売上高売上総利益率とは
- 売上高経常利益率とは ordinary profit ratio
- 当座比率とは Quick assets ratio
- 投下資本利益率(ROI)とは Return on investment
- 投資銀行(Investment Bank)&証券化
- 株主資本比率(自己資本比率)とは Capital ratio, Equity ratio
- 株価収益率(PER)とは Price Earnings Ratio
- 株価純資産倍率(PBR)とは Price Book-value Ratio
- 流動比率とは Current Ratio
- 現在価値とは何か? What is Present Value?
- 総資本回転率とは total asset turnover
- 総資産利益率(ROA)とは Return on assets
- 負債比率とは Debt Equity Ratio
- 財務諸表とは?BS PL CS
- 責任銀行原則 Principles for Responsible Banking
- 資本(自己資本)利益率(ROE)とは Return on Equity
- 配当性向とは Payout Ratio
- 金融工学とは financial engineering
- 銀行の機能とは? 金融仲介・信用創造・決済機能
- 1株当たり純利益とはEarnings per Share(EPS)
- 3つのコーポレート・ファイナンス Corporate Finance
- Alexa Rank(順位)
- DaaS Device-as-a-Subscription
- DSP SSP RBT DMP
- KGI KSF KPIの設定
- LPO Landing Page Optimization
- PASONA(パソナ)の法則 Problem Agitation Solution Narrow down Action
- RFM分析 recency, frequency, monetary analysis
- ROS/RMS分析 ROS/RMS Analysis
- SEOとSEMの違い Search Engine Optimization Search Engine Marketing
- 【まとめ】インターネット広告における主な指標 advertisement indicator
- アトリビューション分析 attribution analysis
- アドネットワーク advertising network
- アドベリフィケーション Ad-verification
- アンバサダー、アドボケイツ、インフルエンサー Ambassador Advocates Influencer
- インターナルマーケティング7つの方法 Internal Marketing
- インバウンドマーケティング inbound marketing
- エスノグラフィ(行動観察法)ethnography
- ゲリラ・マーケティング Guerrilla marketing
- ゲーミフィケーション Gamification
- コトラーの「純顧客価値」とは Net Customer Value
- コトラーの競争地位別戦略 Kotler’s Competitive Position Strategy
- コピーライティング Copywriting PREP法
- コーズ・リレイテッド・マーケティング Cause-related marketing
- サービスマーケティング service marketing
- サービス・ドミナント・ロジック Service Dominant Logic
- サービス・プロフィット・チェーン Service Profit Chain
- サービス・マーケティングの7P Service marketing7P
- ショウルーミング Webルーミング showrooming
- ソーシャルグラフ social graph
- ソーシャルリスニング・傾聴 Social Listening
- ソーシャル戦略 Social Platform Strategy
- ダイレクト・マーケティング Direct Marketing
- トリプルメディア Triple Media
- ネイティブ広告 Native advertising
- ハルシネーション ハルシネイション Hallucination
- ハワード=シェス・モデル Howard & Sheth model
- バートルテスト Bartle Test
- プログラマティック・バイイング programmatic buying
- プロダクト・プレイスメント Product Placement
- ペルソナ(persona)
- ホリスティック・マーケティング Holistic Marketing
- マズローの欲求5段階説
- マーケットシェア&マインドシェア ポジショニング戦略 positioning strategy
- マーケティングとは What is Marketing?
- マーケティングの本質とは Essence of Marketing
- マーケティングの起源 Origin of marketing
- マーケティング戦略策定プロセスの全体像 Marketing Strategy
- マーケティング戦略4P(マーケティング・ミックスMM) Product Price Place Promotion
- ラテラル・マーケティング Lateral Marketing
- リスティング広告 検索エンジン連動型広告 PPC広告 Paid Listing
- 多変量解析 multivariate statistics
- 定量分析手法多変量解析ROSRMS
- 期待不確認モデル expectation disconfirmation model
- 炎上マーケティング flaming marketing
- 経験価値マーケティング Experiential Marketing
- 行動ターゲティング広告とリターゲティング BTA behavioral targeting advertising,retargeting advertising
- 製品ライフサイクル Product life cycle
- 顧客生涯価値(ライフタイムバリュー)LTV(Life time Value)
- DAGMAR理論 DAGMAR Theory
- SERVQUAL(サーブクオル)モデル
- BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)
- DellのBTO Build To Order
- EVA Economic Value Added
- MECE(ミッシー)
- PDCA &BSC&OODA
- PEST分析 ペスト分析
- SDGsとは?
- SMART Specific、Measurable、Achievable、Related、Time-bound
- SWOT分析とクロスSWOT分析
- VRIO分析
- ★BCGのアドバンテージマトリックス Boston Consulting Group's Advantage Matrix
- ★マッキンゼーの7Sフレームワーク McKinsey 7S framework
- 「帰納法」Inductive Approachと「演繹法」Deductive Approach
- 【コア・コンピタンス】とは 模倣可能性・移転可能性・代替可能性・希少性・耐久性
- アンゾフの製品市場マトリクス(マトリックス)成長ベクトルProduct-Market Growth Matrix
- イノベーター理論とキャズム Innovation Theory & Chasm
- エフェクチュエーション(effectuation)&コーゼーション(causation)
- コーペティション経営 Co-opetition Strategy
- サンクコスト(埋没費用)バイアス
- シナリオプランニング Scenario planning
- タイムベース競争戦略 time-based competition
- デコンストラクション deconstruction
- デザイン思考 design thinking
- デジタル・フォレンジック Digital forensics
- デジュリスタンダード&デファクトスタンダード 2つの標準化(対義語) 具体例
- ネット・プロモーター経営(NPS)Net Promoter Score
- ハインリッヒの法則 Heinrich's law
- ピラミッドストラクチャー(構造化)
- フリー戦略
- フレームワークとは Framework
- ブルー・オーシャン戦略 Blue Ocean Strategy
- ポーターのCSV Creating Shared Value
- ポーターのバリューチェーン(価値連鎖)分析
- ポーターのファイブフォース分析 Porter five forces analysis
- ポーターの3つの基本戦略 Porter’s three generic strategies~ lower cost, differentiated focus
- ランチェスター戦略 弱者の戦略
- リバース・イノベーション Reverse Innovation
- 仮説思考 hypothesis thinking
- 全社戦略・事業戦略・機能別戦略 Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy
- 新商品や新サービスを作り出す15の発想法
- 暗黙知と形式知(SECIモデル)
- 破壊的イノベーション Disruptive innovation
- 魚は頭から腐る
- 3C分析(Customer, Competitor,Company )